牡牛座のあなた
全体運はあまりよくありません
特に旅行などアウトドアは避けたほうが吉
恋人とはちょっと寂しい思いをしそう
健康面は肩こり、睡眠不足に要注意です
「うわあ、やな感じだなあ」
6月中旬、神奈川県警捜査一課で、岬刑事が週刊誌を読みながらふとそんなことを呟いた。
「何か事件でもあったんですか?」
岬とデスクを並べる新人刑事円谷冴子が調書から目を上げて、先輩刑事に問いかけた。
「いや、そうじゃなくてさ」
と、岬刑事は週刊誌に掲載されている星占いのページをかわいい後輩に見せてやった。
「俺、牡牛座なんだけどさ、見てよこれ。今週の運勢、いいことひとつも書いてないんだよ?なんかこういうのって嫌だろう?あ、冴子ちゃんのも見てやるよ。君、星座なんだっけ?」
「牡牛座ですけど」
冴子は、何だそんなことか、と言わんばかりに興味の失せたトーンで答えた。
「ありゃりゃ、君も牡牛座か?お互い今週は気をつけような」
何を気をつけるんだか……。
冴子は呆れたようにため息をついた。
「おいおい、岬君、星占いなんて気にしてるのか?」
湯呑茶碗を手に二人の会話に割りこんできたのは、上司である九条啓介警部補だ。九条は岬の週刊誌を覗き込みながら言った。
「だいたい、世間の人間の運勢をたったの12通りに分類してしまうなんてちょっと乱暴過ぎやしないか?日本人だけでも1億3千万人はいるんだぞ。ってことは、1千万人以上の日本人が今週同じ運勢を持っていることになる。ちょっとそれはありえないだろ」
「いや、それを言っちゃあ、身も蓋もないですよ、警部補。そういう諸々は分かった上で読んでるわけですから。それに何だか神秘的じゃないですか、自分の生まれた日で、その日その日の運勢があるっていうのは」
「まあ、そういうこともあるかも知れませんけど、この占いに限ってはかなりいい加減だと思いますよ」
冴子は調書を閉じて、冷めたコーヒーを啜った。
「まず第一にアウトドアは避けたほうが吉ってところですけど……今、6月で梅雨の真っ只中です。旅行に出かければ雨になる確率は高いわけですから当然出かけないに越したことはないわけです」
「うむ、確かにな」
九条が窓の外に目をやると、霧雨が重力に逆らうことなくひっきりなしに降り注いでいる。彼は、昨日からの雨天で今日も傘をさしての出勤だったことを思い出した。
「第二に恋人とはちょっと寂しい思いをしそう、というところですけど、例えば週に3回会っている恋人がいるとしましょうか。そうすると、それが増えればはずれ、減ればあたりというわけで、確率は1/2です。ただ、こういうものを読む人はいわゆる他者依存型の典型の人、つまり、あたるという前提で読んでいる人がほとんどでしょうから、仮に会う回数が普段より多かったとしても会話がはずまなかったとか、ちょっとした口論があったとかすれば、ああ、やっぱり占いのとおりだったと思い込んでしまうものです」
「ひえー、まるでプロファイリングだな、冴子ちゃん」
岬刑事は大げさに驚いて見せるも、そんな揶揄には気にも止めずに冴子は先を続けた。
「駄目押しが、健康面のくだりです。冷静に考えてもみてください。肩こりや睡眠不足などというものは、程度の違いこそあっても、大抵の人は自覚症状をもっているものです。これは星座やシーズンとは全く無関係の話です。だいたいが他の星座のところを見ても分かるように、書いている内容がすべて抽象的かつあいまいな表現ばかりで、とらえようによってはどうとでも解釈できるものばかりです。となれば占いを信じている人は自分の環境に適合するように勝手に解釈するでしょうから、占いが当たる確率が高くなるのは自然の理というわけです」
「冴子ちゃん、君、ときどきえらいきついこというよねえ」
岬刑事が笑いながらそうコメントするが、竹を割ったような性格の彼は別段、不快に思っている様子ではない。
「ナルホドなあ、ま、もっとも、私はハナから占いなんて信じないがね」
九条警部補は自分のデスクに戻ると、デスクの上に置きっぱなしにしてある新聞をそそくさと折りたたんだ。
(さっきまで、占いの欄を読んでたなんて言えないよなあ……)
九条は切れ者の冴子に感心する一方で、切れすぎるのも上司としては扱いにくいなあなどと思っていた。
まあ、それも贅沢な悩みではあるが……。
ふいに電話が鳴って、九条が受話器を上げる。
「はい、捜査一課……分かった」
手短に済まされた電話のあと、九条は岬たちに声を掛けた。
「コロシだ。現場に急行するぞ」
「え〜、アウトドアは敬遠したいんですがねえ」
などと、愚痴らしきものをこぼしつつ、席を立つ岬。
冴子はもうドアを開けて、傘の準備をしている。
「さあ、早く行きましょう」
心なしか笑みを覗かせている冴子。どうやら彼女は仕事が好きで好きでたまらないらしい。
現場は被害者の自宅だった。九条たちが到着すると、レインコートを着た警官たちが家の回りにロープを張って現場保存の職務を全うするべく、多くの野次馬たちを塞き止めていた。九条が代表して警官に腕章を提示すると警官は「ごくろうさまです」と敬礼をし、ロープを引き上げてくれた。
九条は敬礼をかえして、ロープをくぐり、その後を岬と冴子が続く。
「あの、ちょっと……」
警官が冴子を呼びとめる。
「何か?」
「すいませんが、関係者以外の方は入れませんので……」
岬は思わず噴きだした。異常に若く見えてしまう冴子だけに、こういうことはよくあるのだが、やっぱり笑ってしまう。
九条も笑いそうになるのをこらえながら警官に口添えする。
「ああ、彼女は私の部下の円谷巡査部長だ」
「はっ、こ、これは大変失礼しました!」
警官は可哀相なくらい直立不動で最敬礼して冴子に謝った。まさかこんな若い(しかもカワイイ!)女の子がキャリアで自分よりも階級が上だとは思いもよらなかったことだろう。
「いえ、気にしてませんから……」
冴子はニコリともせずにそう言い残し、被害者宅へ入っていったのだった。
殺 害現場は被害者の書斎だった。遺体はまだ片付けられていない。被害者は中年の男で、部屋の机に突っ伏すようにして死んでいた。後頭部に挫傷の痕が認められ、背後から殴られたものと推測される。凶器は足元に転がっている灰皿らしい。ひとりの刑事が九条たちに歩み寄り状況を説明した。九条も顔見知りの安原という刑事だ。
「えー、被害者は重森尚(しげもりひさし)、48歳、金貸しです。家族はおらず、ひとり暮しでした。応接テーブルにまだ冷めてない紅茶が二人分ありましたので、おそらく被害者と犯人のものと思われます」
「顔見知りの犯行か……ん、まてよ。冷めてない紅茶と言ったな?どういうことだ。紅茶なんて、ものの数分で冷めてしまうぞ」
「ええ、遺体の発見が早かったもので……あ、こちらが発見者の方です」
安原刑事は背広姿のサラリーマン風の男を九条に紹介した。
その男はぺこりと一礼し自己紹介した。
「山元です。山元一郎と申します」
山元はハンカチでしきりと汗を拭いながら話し始めた。
「私、健康器具のセールスをしておりまして、ちょうどこの家の前を通りかかったところでした。そしたらここから悲鳴らしきものが聞こえてきまして……雨の音ではっきりと聞き取れたわけではなかったので自信はなかったんですが、まあ、お宅を訪問するにはいい口実になるかなと思いまして……ただ、お昼時だったのでどうしようかなとも思ったんですけど……」
「12時丁度のことだったそうです」と、安原刑事が補足説明する。
「よくはっきりと時間がわかりましたね」と、岬刑事がしごく当然な質問をする。
「ええ、悲鳴を聞く直前に腕時計を見たんです。そしたらきっかり12時で……そういうきりのいい時間だったりしたものですから、はっきりと覚えてました……あの、刑事さん、まさか私が疑われているんじゃないでしょうね」
「まずは、全て話してみてください。話を聞かないことにはなんとも言えませんから」
九条は苦笑まじりに先を促した。
「えっと、玄関のドアの前まで行くと、ドアが少し開いてたんです。で、無用心だなあと思いまして、チャイムを何度か押してから玄関まで上がってみました。靴があったし、これは人がいるなと思い、声を掛けたんですが返事がありません。そしたら奥の方でばたばたと走っていく足音がして……こりゃあ尋常じゃないぞと中へ入っていったんです」
「それで?」
「そしたら、ひとつだけ開いているドアがあったんで中を覗いたら……」
「死体とご対面ってわけか」
「ハイ、私もう吃驚しまして、それで警察に電話を……」
相当動揺しているようだが、第一発見者の証言におかしなところはないようだ。おそらく犯人は突然の来訪者に慌てて、勝手口からでも逃げ出したのだろう。
「確かに山元さんの言うとおり、被害者のサイズとは違う靴が一足だけ玄関にありました」
そばにいた鑑識係員がビニール袋に入った靴を九条に差し出した。九条たちは犯人のものと思しき黒い靴をしげしげと眺めた。
「他に犯人は何か残していかなかったのか?」
「はい、どうやらその靴だけのようです」
「そうか……まあ、凶器なりに指紋でも残っていればありがたいがな」
一通り聞き終えた冴子は、早速遺体の方へ近づいて観察を始めた。そして、いろんな角度から遺体の状態を検分する。
「警部補、被害者はペンを握ったまま絶命したようですね」
被害者の上体の下に、まるで隠すようにしてある一枚のメモを見つけた。
「これって……」
「またダイニングメッセージか……」
岬はいつぞやと同じ過ちをしていた。また言い間違えたら今度こそ、それを言うならダイイングメッセージだ、と訂正してあげよう。
冴子は心にそう決めて、今回ばかりは聞き流してあげることにした。
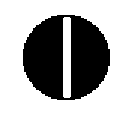
「90度回転させると、進入禁止の道路標識にも見えないこともないんだけど……あ、分かった!」
岬刑事はふいに閃いて、ポンと手を打った。
「これって天気記号じゃないですか?白マル(○)は快晴、黒マル(●)は雨、二重マル(◎)は曇りとかっていうアレですよ!」
「しかし、天気記号にこんなのがあったか?黒マルで中央に白い線が入っているのなんて……」
「晴れのマークの色違いってところですよね……でも、きっと何かあるはずですよ、それが犯人の名前を示しているに違いありません。警部補、あとで調べておきますね」
岬刑事は己の発見に自己陶酔しているらしく、鼻息も荒くそう宣言したが、冴子がすぐさま水をさした。
「そんな天気記号なんてないですよ、岬さん」
「ななな、何ぃ!?冴子ちゃん、どうしてそう断言できるんだ、ええっ?」
能天気な岬が冴子に詰め寄るも彼女は柳に風、蛙に小便、焼け石に水だ。
「だって、天気記号なんてせいぜい20コくらいしかないんですから、こんな図柄が存在しないことくらい誰にだって分かります。まあ、国際式なら100コくらいあるんですけど、あまり一般的ではないのでこの場合は考えに入れなくていいでしょう」
(誰にでも分かるとは思えんぞ、それは)
九条警部補は、こんなふうに時折垣間見せる彼女のマニアックな知識に舌を巻いた。
(一体、そんな豆知識、どこで仕入れてくるんだ?まさか、昔、気象予報士を目指してました、なんて言いだすんじゃないだろうな)
「いずれにせよ、このメモが事件と無関係とは考えにくい。検討してみる必要がありそうだ……いや、それにしてもガイシャは几帳面な男だったようだな。見たまえ、私物には大概名前をつけている」
九条の言うように、ハンカチには刺繍が、手帳にはシールが貼られていて、それらにはすべて「重森」と記されている。
「100円ライターにまで名前が書いてありますよ。これは几帳面というよりただのケチなんじゃないですか」
岬が死人を前にしてひどいことを言う。
「あのォ……九条警部補」
安原刑事が恐る恐るといったふうに九条に尋ねた。
「ところで、この女性は警部補の娘さんか何かですか?たとえ身内の方とはいえ、殺 人現場に無関係な人を入れるのはちょっとマズイと思うんですけど……」
言うまでもない。安原刑事は冴子を指してそう忠告しているのだ。
「そうですよ、警部補♪」
岬刑事は悪乗りして、笑いをかみ殺しながらそう言った。
しかし、冴子は彼らの誤解など眼中になかった。彼女はひとたび考え始めると、完全に周りが見えなくなってしまうのだ。
犯人は玄関から入り、書斎で被害者を殺 害し、突然の来訪者に追いたてられるように裏口なり勝手口なりから逃走した……。
なのに何故……?
6月15日火曜日。雨はいまだ止む気配がなかった。
その翌日。
聞き込みを終えた岬刑事が、事件の経過報告を手土産に戻ってきた。
岬が九条のデスクの前で手帳を開くと、捜査一課の猛者たちがわらわらと集まってくる。
「まず指紋の件ですが、残念ながらティーカップと灰皿はきれいに拭き取られていました。ただ、予期せぬ訪問者で犯人も焦ったらしく、テーブルなどから被害者以外の指紋がいくつか検出されました。そのうちで被害者に恨みを抱いていたと思える人物は3人です。いずれも金銭がらみでトラブっていたようですね。3人とも犯行時刻のアリバイがなく、しかもご丁寧に靴のサイズまで一緒でした」
「そうか、取り合えず容疑者はある程度絞られたわけだな。で、その3人というのは?」
岬刑事は隠し撮りしてきた3人の顔写真を机の上に並べて見せた。彼は聞き込みやら指紋採取やらにかなり苦心したはずなのだが、そんなことはおくびにも出さず淡々と報告を続けた。
「一人目は赤口明(セキグチ アキラ)30歳。彼はシナリオライターで重森宅の二軒先の借家に住んでいます。ずっと家で仕事をしていたそうですが、一人暮しで来客もなく、アリバイを証明することはできませんでした。二人目が久留米葵(クルメ アオイ)40歳。印刷会社の営業マンで一日中外回りでしたが、やはり犯行時刻の前後の所在がはっきりしていません。本人はその時間、現場近くの公園の東屋で愛妻弁当を食べていたと言っていますが、やはり目撃者は見つかりませんでした。それと三人目が黄川田涼(キカワダ リョウ)20歳。彼は重森宅近くの工事現場で交通整理のアルバイトをしていました。午前11時から午後1時頃まで休憩時間で現場を離れていたようです。本人はアパートに帰って食事をしていたと言っていますがこちらも一人暮しで証明できる者がいませんでした。3人とも被害者宅へは最近行ったことがあると認めましたが、あの日は近づいてもいないとのことでした」
「第一発見者の山元氏はどうなんだ?」
「こちらは完全にシロです。被害者との繋がりはまったくありませんでした」
「そうか……すると犯人はこの3人の中の誰かという可能性が極めて高いな」
「困りましたね、現場に残された記号の件も気になるし……」
円谷冴子はふと誰にともなく呟いた。
「やっぱりそういうことだったんだ……」
「え、何がやっぱりなんだい?」
「いえ、たぶんそんなことだろうとは思ってたんですけど……念のためちょっと調べてみます」
冴子はそう言って、辞典を引っ張り出してくるとおもむろにページを繰り始めた。
やがて、彼女はあるページで手を止めた。
「警部補、ここを見てください」
「あっ!これは……そうか、こいつが犯人だったのか」
「ええ、間違いありません。今の岬さんの報告を聞いて確信しました。犯人はこの人です!」
そして、冴子は自信たっぷりに一枚の写真を取り上げたのだった……。
