師走である。
今年も残すところ、あと1ヶ月あまり。
新人刑事円谷冴子は、岬刑事とともに聞き込みに奔走していた。
事件はいつも平行して起こる。そして、未解決のまま迷宮入りになるものも決して少なくはない。
今抱え込んでいる事件もまたそれに類するものだった。
買い物帰りの中年女性に、犯人と思しき男の写真を見せるも全く無視されてしまった岬刑事が、肩を落として冴子のもとにやってくる。
「また、質問拒否されてしまったよ。最近の人たちは協力的じゃなくて困るなあ」
「まあ、あんなことがあれば、それも仕方のないことかもしれませんね」
冗談ぽくぼやく岬に、冴子がそう応える。
「ばっ、ばか!……冴子ちゃん、滅多なこと言うもんじゃないよ」
岬が慌てて口にチャックをするゼスチャーをして、かわいい後輩を窘める。
「みんな、そのことではぴりぴりしてるんだからさ。臭いものに蓋ってわけじゃないけど、今は襟を正して嵐が過ぎ去るのを待つしかないんだよ」
「でも、岬さん……」
「さあ、聞き込みを続けよう」
岬刑事は冴子の肩を叩いて、それ以上は言いなさんな、とばかりに聞き込みを再開する。
冴子の言う『あんなこと』とは、言うまでもなく神奈川県警内部で起こった一連の警官不祥事事件のことである。某所轄署内で発覚した集団警ら隊の連続暴行事件や女子大生脅迫事件などが大々的に報道され、神奈川県警は極めて不名誉な形で全国区の注目の的となった。暴力団員から手に入れた証拠物件を私利私欲のために使ったり、実弾入りの拳銃を突きつけるなどの常軌を逸脱した部下いじめ、更には、内部の不祥事を徹底してもみ消そうとする当局の利己的な姿勢など、俄かには信じがたいセンセーショナルな話題となり、警察に対する大衆の不信感を大いに募らせた。
尤も、県警察本部の末端に籍を置く冴子たちには直接関係のないことではあったし、そんな事実はニュースを見て初めて知った寝耳に水のことではあったが、県民感情はそうもいかない。『神奈川県警=裏で何をやっているか分からん奴ら』というレッテルを貼られ、誠実に職務を遂行する彼女たちもまた同罪、いっぱひとからげというわけである。
冴子は街往く人々の疑惑と軽蔑を含んだ視線が痛かった。そして悔しかった。岬もきっと内心は同じ思いだろう。いや、ほとんどの同業者たちはそう思っているに違いない。組織とは……公僕とは辛いものである。この遣る瀬なさをどこにぶつけたらいいものか……。
いずれにせよ、地域住民の平和を守る国家警察の信頼は地に落ちた。しかし、それもやがて時とともに風化してしまうだろう。あんなに憤りを感じていた人々の記憶からも消えて失せてしまうに違いない。そう考えると、冴子はひどく虚しさを覚えずにはいられなかった。
犯 罪者たちもまた同じ。
すっかり過去の事件として記憶の片隅に追いやられていたグリコ森永事件も来年2月には時効を迎える。その時は再び巷の話題にのぼるだろうが、すぐにまた新たな事件に掻き消されてしまうことだろう。
連続猟奇殺 人犯、狩野邦彦(かのう くにひこ)の犯 罪も3年前にすべて時効となった。
そして狩野は、時効成立とともに全国のお茶の間にその姿を曝け出した。
空前絶後、前代未聞、絶対無比。
当時、『究極の知能犯 罪者』の名を欲しいままにした狩野は、テレビ生出演をやってのけたのだ。
タイトルもズバリ「究極の知能犯 罪者ライヴ・オン・エアー〜衝撃!今夜明かされるあの事件の真相!!〜」。
狩野はテレビ局に対して、警察には内密にという条件付きで、自分が殺した被害者たちの惨殺死体と共に撮ったツーショット写真及びそれに使った数々の凶器を提供した。犯行に使用された凶器の形状はある程度判明していたが、それは世間一般には公開されていなかった機密事項である。であるにも拘わらず、のちにそれらがことごとくぴったり一致していたことが明らかになった。これこそ彼がほぼ100%犯人である証明である。
当然、時効を迎えたばかりの殺 人犯を警察にも報せず、全国放送に流してしまった当局は散々叩かれたものだが、彼ら曰く「まさか本物の犯人だとは思わなかった!」である。視聴率至上主義の業界にあって、ヤラセだろうと何だろうと視聴者が興味を持ちさえすれば何でもアリの大歓迎なのだ。
ともかく狩野は、その番組出演を最後に姿を消した。
17人もの罪なき者たちを殺 害しつづけた彼のことは、3年経った今では誰の口にものぼらない。
どんなにショッキングな事件の記憶も時が緩やかに溶かしてしまう。
しかし、絶対に忘れない者も僅かにながらいた。
円谷冴子もそのうちの一人だった。
――――――私の大切な人を奪った者を決して忘れはしない。
狩野邦彦は必ず戻ってくる。冴子はそう確信していた。
なにが究極の知能犯 罪者だ。奴はただの殺 人鬼。人の皮を被った鬼畜。単なる自己顕示欲の塊ではないか!見た目が派手な犯 罪ばかりを重ね、あげくテレビにまで顔を出す。皺ひとつない高級そうなスーツに身を固め、口元には軽い笑みさえ浮かべ反省の色など全く見せず、いっぱしの文化人を気取って犯 罪を芸術だとまで言ってのけた男だ。
ならばこそ彼は、きっといつの日か表舞台へと帰ってくる。
己が世間から忘れ去られることが堪らないに違いない。
そのときこそは、きっとこの手で……。冴子はそう心に決めていた。
刑事の職務は犯 罪者を捕らえること。決して裁くことではない。
そんなことは分かりきっている。だが、狩野邦彦だけは別格だ。
あの男だけは、必ずこの手で裁きを……鉄槌を下す。
そして、その瞬間こそが私がこの仕事を辞めるときだ。
――――――僕は僕が殺めた人たちの人生を全部背負って生きているんです。
学生時代の冴子がブラウン管越しに見た狩野邦彦の最も印象的な台詞である。
もし、あいつに合間見える機会があったなら、真っ先にあの言葉を否定させる。狩野邦彦はその存在自体が罪なのだ!
「冴子ちゃん、あまり悩むなよ」
唇をかみ締め、険しい表情を見せている冴子に岬刑事が気遣いの言葉をかける。
岬をはじめ彼女の同僚たちは誰も彼女と狩野邦彦の関係を知らない。つまり岬は内部の不祥事に対して冴子が悩んでいると誤解しているのである。
「……っと、電話だ」
ふいに岬の携帯電話が着メロを奏でた。
「はい、岬です……あ、結構近いですね。10分で行けます……え、ホントですか!分かりました。じゃあ、また後で」
電話を終えた岬が弱ったなあとばかりに眉を下げる。
「岬さん、また事件ですか?」
「ああ、コロシだってさ。九条警部補が先に現場に向かっている……ただちょっと厄介なことがあってね」
「厄介なこと?」
「うん、今回の事件、超有名人が絡んでるみたいなんだ」
要するに、事件がこじれるとマスコミが群がってくるぞ、というわけである。こういう時節柄だけに上層部としては速やか且つ穏便に処理してしまいたいところなのだろう。
「誰ですか、その有名人って?」
冴子の問いに、岬刑事は辺りを憚るように声を落として耳打ちする。
「春日彰信(かすが あきのぶ)だよ」
しかし、冴子はきょとんとして言ったもんだ。
「誰ですか、それ?」
「えっ、ウソぉ!冴子ちゃん知らないの?今『CAN NOT』ってドラマに出てる役者さんだよ。女性問題で写真週刊誌によくスッパ抜かれている色男と言った方が分かりやすいかな。いや待てよ、元アイドルグループ『TRUTH』のメンバーって紹介の仕方もあるな」
と、懇切丁寧に解説する岬刑事。彼は案外ミーハーな男なのかもしれない。ところが一方の冴子はまだピンと来ないようだ。
「ええと、すいません。私、あまりドラマとかは見ないものですから……」
「いや、別に謝ることないけどさ……まあ、実物を見れば思い出すかもしれないな。とにかく急ごうや」
そう言って、タクシーを拾おうと車道に身を乗り出す岬。
「でも、ちょっと安心したよ」
「何がですか?」
停まったタクシーに乗り込みながら岬が呟く。
「いや、冴子ちゃんでも知らないことがあるんだな、ってさ」
サングラスにニット帽、顔の下半分をマフラーに隠した男が歩いている。
一応、変装のつもりである。
男の名前は春日彰信といった。
彼は密かに、事務所を移籍し独立することを考えていた。
――――――今の事務所は、どうも信用がおけない。後輩にばかりいい仕事をふって、この俺にはバラエティ番組のリポーターなんぞを押しつけてくる。俺は話題のドラマ『CAN NOT』で主演を張っている男だぞ!なのに、次のドラマの仕事は今だ来ていないという。ったく、どういうこったよ、そりゃあ。いや、それもこれも事務所が俺に見切りをつけたということなのだろう。たまに持ってくる仕事といえば、「特別出演」だの「友情出演」だのばかり。要は態のいい端役じゃねえか。俺は刺身のツマじゃねーんだ!
これがいい機会だ。俺は『CAN NOT』を足がかりにのし上がってみせる。音痴だとか大根役者だとかルックスだけで保っているとか、言いたい奴には言わせておけばいい。こっちは長年この世界で飯を食ってる。それなりの人脈を持っているんだ。有能なスタッフをかき集めて、俺の事務所を旗揚げしてやる……。
春日は、在る女性のマンションに向かっていた。その女性とは遠い昔の恋人だった。彼女は某テレビ局のディレクターをしている。若い感性と独創力で異例の出世を果たした意思の強い女だ。
春日は意気込んでいた。
――――――今日こそはあいつをモノにしてみせるゼ。
もちろん、それは女としてという意味ではない。仕事上のパートナーとしてだ。彼女とは恋人を経て、今は言わば戦友といった間柄である。自分が独立する上で彼女を引き込むことは絶対に必要だと彼は考えていた。
春日は女性関係では随分と浮名を流してはいたが、その大半は事実無根だった。しかし、マスコミの前での彼はそのほとんどを否定しようとはしなかった。スキャンダルもスターの勲章だというのが彼のポリシーだったからである。
――――――俺が本気になったのはあいつくらいのもんだったな。
そんな感傷に浸ってるうちに、彼女の部屋の前につく。
そしてチャイムを押す。
されど一向に返事は返ってこない。
「おかしいな、いないはずはないんだが……」
春日は訪問するにあたり、あらかじめ電話をいれて約束を取りつけている。にもかかわらず在宅していないというのは、彼女のきっちりした性格からして考えにくいことであった。たとえ急用ができたとしても断りの連絡ぐらい入れてくるはずなのだ。
「おい、いねえのか?」
訝しく思った春日は試しにドアノブを回してみるが、やはり鍵が掛かっている。
「ひでえな、出掛けてンのかよ。ったく、仕方ねえな……」
春日は一瞬躊躇したが、昔、彼女から貰った部屋の合鍵をセカンドバックから取り出した。捨てるに捨てられず、返す機会を逃していたのだが、なんとなく……そう、お守りがわりに持っていたのだ。
――――――まさか、これを使うことがあるとはな……。
「約束破るそっちが悪いんだぜ。中で待たせてもらうよ」
軽い後ろめたさを覚えつつ鍵を差し込む。カチャリと冷たい音がしてドアが開いた。
しかし、彼はそれでも中に入ることができなかった。
ドアにチェーンが掛けられていたからだ。
――――――おかしいな。チェーンが掛かってるってことは中にいるってことだよな。
春日はひどく胸騒ぎがした。
――――――ただごとじゃないぞ、こりゃあ。
彼は、たまたま通りかかったマンションの住民に依頼して、管理人を連れてこさせた。
「ちょっと、困るんですよねえ」と言い渋る管理人からペンチを調達しチェーンを断ち切る。
「心配すんな。俺はこの部屋の主の知り合いだ。責任は俺が持つ」
管理人を入り口に待たせておいて部屋に入る。
入ってすぐのダイニングキッチンに彼女の姿はなかった。更にリビングの引き戸を開けたがそこにも見当たらない。やがて彼はベランダへ続く半透明のガラス戸が開いていることに気がついた。
ドクドクと胸の鼓動が高鳴る。
ゆっくりとベランダに近づく。
風にたなびく洗濯物。
その下には……
「そこで、死体を発見したと……こういうわけですね」
九条警部補が淡々とした口調で尋ねると、第一発見者の春日彰信は青ざめた顔で頷いた。
「ええ、まあ……」
足元には、この部屋の主である井上知佳(いのうえ ちか)の惨たらしい遺体が転がっていた。眉間をボウガンの矢で射ち抜かれている。矢のシャフトはおよそ30センチで、その1/3までが垂直に突き刺さっていた。疑うべくもなくその先端は頭蓋骨を貫通し脳に達している。生前はそこそこ美人だったであろうと想像されるが今は見る影もない。
「ドアには鍵とチェーンが掛かっていたんですよね?」
冴子が確認するように問うと、春日は端正な顔を歪めて今にも泣きそうな態で頷いた。
「誰がこんなひでえことを……」
遺体はベランダのほぼ中央に横たわっていた。部屋に鍵が掛かっていたとなるとボウガンは外から放たれたものと考えざろう得ない。しかし、高級マンションの部類に入るこの部屋は10階の高さにある。しかもこのベランダは土手に面していて、川を隔てた向こうにしか建物はない。
「川向かいのビルが一番近いな。しかし、ここまで届くかどうか……」
そんな疑問を口にする九条に冴子が即座に応じた。
「それは無理でしょうね。凶器がライフルとかであれば別ですが、ボウガンではせいぜい飛距離50メートルが限界です。しかもこれだけ深く刺さっているということは至近距離から撃たれたと考えるのが自然でしょう」
「う〜む、やはりそうなるか。となると、下の土手から撃ち上げるというのもありえんな」
九条がベランダに立って周囲を見回す。
「右隣りの部屋とはベランダが続いているな。しかし、壁で仕切られているから届かない。左隣りの部屋はベランダが離れているが壁がない。矢は左隣りの部屋から撃たれたのかもしれないな」
「ところがそうでもなさそうなんですよ」
ふいに岬刑事が左隣りのベランダに現れて、九条に声を掛けた。
「どういうことだね。岬君」
「ええ、この部屋は空き室だったようでして、管理人さんにも確認しましたが、ここはずっと締め切ったままだったそうです。念のため、中を見せてもらって調べてみましたが、最近、人の出入りした形跡はないですね。ちなみに右隣りの部屋も空き室になってます。あ、見取り図貰ってきましたので今そっちに持っていきますね」
と言い残し、岬が隣りのベランダから消えた。井上知佳のベランダと左隣りのベランダとでは2メートル以上の隔たりがある。見取り図をベランダ越しに渡すことはできなかったのだ。
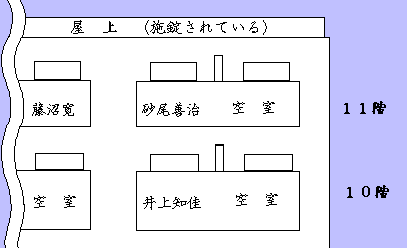
「この図面を見る限り、ここに矢を撃ち込めるのは、藤沼寛(ふじぬま ひろし)の部屋くらいのものだな」
程なく岬が持ってきた見取り図を睨みながら九条が唸った。
「藤沼っていうのは、ガイシャと何か関係があったのか?」
この質問には、聞き込みのプロフェッショナル、岬刑事が答える。
「はい、藤沼寛は浪人生なんですが、井上知佳とは面識があったようですね。間もなくこちらに来てもらうことになっています」
「そうか。それにしても、浪人生の身分でこんないい部屋に住んでるのか。羨ましい限りだな」
「警部補、ところで死亡推定時刻の方は割り出されたんですか?」
「ああ、間もなく報告が入る」
そこへ、鑑識の報告を待つまでもないといった感じで冴子が口を挟む。
「たぶん、死後間もないでしょう」
九条が、ほう、と興味深げに冴子に向き直る。
「どうしてそう思うんだね?」
「洗濯物です」
「洗濯物?」
「ベランダに洗濯物が掛けられたままなんです。昨日は夜まで雪が降っていましたから、これらはおそらく今日になって干されたものでしょう」
確かに、昨日は関東地方全域が初雪に見舞われた。そんな日に外に洗濯物を干しっぱなしにしておくわけがない。一方、今日は打って変わっての晴れ間がのぞき洗濯日和である。遺体の損傷状況から見て、2日以上放置されていたとは考えにくく、彼女のいうとおり、犯行は今日の昼頃に行われたものであると考えられる。
そして、それは間もなく入った鑑識班の報告により見事裏づけされた。
死亡推定時刻は今日の昼10時から11時の間と断定されたのだ。
「よし、藤沼が来たら早速アリバイを聞いてみよう」
と意気込む九条だったが、冴子はなぜかあまり関心を示さず、洗濯物のシーツを手にとって見ている。
「どうした、円谷君」
「はい、このシーツ、少し濡れているのが気になって……犯行があったのが10時前後だとすると、すでに5時間以上干されていたことになりますよね。この天気でまだ渇ききっていないというのは、どうもおかしいなと」
「うむ、確かにな」
「それに、ベランダの手摺ですが……」
「手摺がどうかしたかね?」
「見てください、ここも若干濡れています。なぜだと思いますか?」
なるほど、言われてみれば確かに手摺の中ほどが濡れている。
「さあね、これが何か事件と関係があるとでも?」
九条がそう言って振り返るが当の冴子は既に現場から消えていた。重要参考人、藤沼寛が来るのを待つことなく、である。
